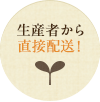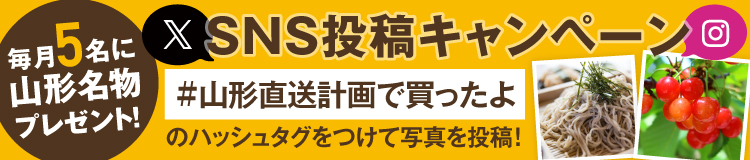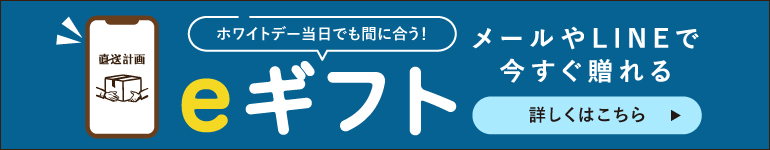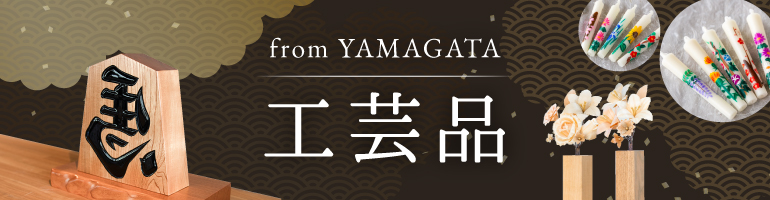米鶴酒造
山形県東置賜郡高畠町 店舗ジャンル:酒蔵・酒造江戸時代初期に創業した高畠町の酒蔵。上杉家の御用酒蔵を務めるなど、古くから高品質な酒が評価され、現在も数多くの受賞歴を誇る。地元での酒米作りにも取り組んでいる。
 「感謝を伝える酒」「縁起の良い酒」という意味が込められた名前
「感謝を伝える酒」「縁起の良い酒」という意味が込められた名前 江戸時代に創業した、品質を重視する酒蔵
高畠町の緑豊かな山間にある「米鶴酒造」は、1697年に創業した酒蔵。酒造りを始めたきっかけには、江戸時代ならではの役職が関係している。「先代によると、年貢米の管理を行う庄屋をしていたそうです。年貢や小作人の取り分では消費しきれなかった米を、酒にしたのではと聞いています。江戸末期には、地元を治める上杉家の御用酒蔵も務めました」と、代表取締役社長の梅津陽一郎さんは語る。明治に入ると、地域にある30件ほどの小さな造り酒屋の中では一番の老舗となり、他の酒蔵の技術指導を実施。その後、大学で醸造学を学んだ梅津さんの祖父が、自ら杜氏となって科学的な知見に基づく酒造りに取り組んだことで、品質を重視する米鶴酒造の基盤が築かれたという。その確かな味と品質がファンの心を掴み、鑑評会やコンテストでは多くの賞を受賞している。
「地域共生」を大切にした酒米作り
米鶴酒造は、地元産の米にこだわる。梅津さんは「1983年に『酒米研究会』を発足し、地元農家と協力して酒造好適米の栽培を始めました。幻の米とも言われる品種『亀の尾』を復活させ、その中から粒が大きいものを選抜して『亀粋(きっすい)』という新たな酒造好適米も開発したんですよ」と、語る。また、酒米研究会が作る米は、米の出来栄えを評価・表彰するため、毎年山形県で開催されている「酒米コンテスト」で4年連続第1位に輝くなど、高い品質を評価されている。地域内で酒米作りを行う背景には、地元への想いがある。毎年休耕地が増え、米の生産量が減っていく中で、何かできることはないかと考えたという。「弊社の行動規範の一つに『地域共生』があります。地域や自然に生かされているという感覚が大事だと思っています」と、梅津さんは力を込める。
食の豊かさに貢献する酒を造る
「米鶴」という名前には、2つの意味が込められている。1つは、稲穂や鶴の立ち姿が、お辞儀をしているように見えることから「感謝を伝える酒」。もう1つは、八十八羽の鶴が末広がりに舞う「縁起の良い酒」。それらを体現した酒でありたいと願って、名付けられたのだそう。そんな米鶴酒造が目指すのは、酒を通じて食の豊かさに貢献すること。「酒は生活に必ずしも必要ではありません。それでも飲まれるのは、豊かな食文化に囲まれて暮らしたいという想いがあるからだと思うんです。そうした想いに寄り添い、貢献できる酒を造っていきたいですね」と、梅津さんは語った。
生産者紹介
代表取締役社長梅津陽一郎
高畠町出身。大学院まで物理学を専攻し、卒業後はエネルギー関係の研究機関に就職。32歳の時に家業の「米鶴酒造」に入った。研究員と酒蔵の仕事は異なる部分が多く、特にコミュニケーションに難しさを感じたという。「酒造りは多くの人と関わります。少し言い方が変わるだけでも伝わりませんし、言葉だけではなく、人となりも見られています。だから、いかに共感してもらえる言葉を使うか、それを伝えるために自分がどういう人間である必要があるのか、ということまで意識していますね」と、梅津さん。また、大切にしているのは笑顔だ。「座右の銘は『笑う門には福来る』。辛い時にも笑顔を忘れないようにしています。注意する時も、笑顔なら悪い気はしないですよね」と、微笑む。
店舗詳細
| 店舗名称 | 米鶴酒造 |
|---|---|
| 住所 | 山形県東置賜郡高畠町二井宿1076 |